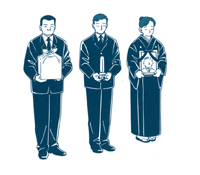
神式の場合もお骨を自宅に安置してある間は、霊前に 、花、ロウソクなどを飾り、洗米、塩、御神酒、果物、菓子、故人の好物を供えます。毎日、水のほかに小さな木皿にご飯を供えることもあります。

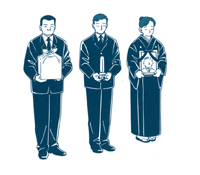
神式の場合もお骨を自宅に安置してある間は、霊前に 、花、ロウソクなどを飾り、洗米、塩、御神酒、果物、菓子、故人の好物を供えます。毎日、水のほかに小さな木皿にご飯を供えることもあります。
意分骨の必要があるのは、郷里が遠くて、そこに近親者や親類が多く住み、法要のたびに墓地まで出向くのが困難だからとか、故人の親がどうしても先祖と同じ墓に葬りたいという場合などです。
分骨したいときは、火葬のときに骨壺を二ツ用意してもらうよう葬儀社に頼み、火葬場で分骨するのがいちばんよい方法です。火葬場で分骨しなかったときは、寺や神社に頼んで分骨してもらいます。家庭で分骨することはしません。分骨の際には、なるべく僧侶などに読経してもらうとよいでしょう。
なお分骨を忌みきらう人もいますが、仏教では釈迦の骨は八ヶ所に分骨され、弟子たちの手でそれぞれ手厚く供養されているところからも、分骨はいけないとされる理由はありません。神道やキリスト教においてもとくに教義のうえから分骨を禁ずる考え方はないでしょう。
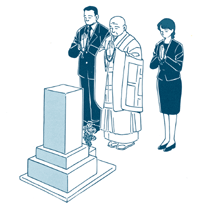
四十九日がすぎると、あとは百ヵ日(百日目)を迎えるまでとくに大きな法要は行いません。百ヵ日は近親者、友人、知人、僧侶を招いて法要を行いますが、内輪にすませることもあります。昔は百ヵ日に「施餓鬼会」といって無縁仏の供養も合わせて行う習慣がありました。百ヵ日で法要は一段落し、あとは一周忌になります。
初七日や七七日のようにかなり大ぜいの人を招いてする法要と内輪の法要とでは謝礼の額も異なります。大ぜいの人を招く場合は、一万円以上の謝礼金のことが多いようです。表書きは「御布施」、または「御経料」です。そのほか「御車料」が必要で、接待をしない場合は「御膳料」も差し上げるのが礼儀です。
春・秋・二季のお彼岸は六道をつとめる期間です。布施(自分の持っている能力をおしまずに人々のために役立てる)、持戒(人の迷惑になるようなわがままはやめ、決められた事はきちんと守る)、忍辱(苦しい事も我慢し、それに打ち勝って進む。また、むやみに腹を立てない)、精進(何事にも力一杯がんばり怠らず努力する)、禅定(常に反省をしながら落ち着いて行う)、智恵(物事を正しく見極める心を自分の中に育てる)の実践項目を最小限でも良いから「やろう」という心を一週間もつことです。それが、そのままそっくりご先祖さまへの供養につながります。
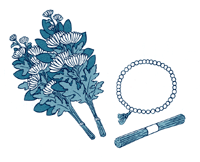
初盆の準備故人の死後はじめて迎える新盆の供養はとくに丁重に営みます。仏壇の前には、精霊棚を設け、初物の農作物でつくった供物を飾り、供養膳に精進料理を盛って供えます。白玉だんごや果物、好物なども供えます。なおこの供物は墓前にも供えるので用意します。またお盆の間は、精霊に自分の家を教えるために、仏壇のそばとか軒先に、岐阜提灯や新盆灯篭を飾るものとされています。この提灯は、新盆を迎える家でととのえたり、親せきや知人からお盆の前に贈られたりします。なお、新盆には僧侶に読経を頼みますが、お盆は僧侶がもっとも多忙なときですから、早めに依頼しておかなければなりません。
永代供養とは、仏の供養をするべき施主が遠くに行っていたり、施主となるべき人が死に絶えてしまっても、菩提寺が代わって永久に法要を営んでくれるというとりきめです。このごろは核家族化しているうえに、子弟が外国に居住してなかなか帰国しないなどという例もあって、万一の場合を考え、永代供養の申し込みをする人がふえてきたようです。永代供養料は寺によっても違いますが、まとまった金額を寺に渡すと、寺ではそれを記録し、必要なときまで施主の名前で信託預金などをして、永代供養ができるようにはからってくれます。
ただし永代供養を申し込んだからといって法要をしなくてよいというのはあやまりで、施主のいる間は永代供養の約束とは別にふつうの法要をしてもらいます。永代供養を申し込むのは、三回忌か七回忌あたりのことが多いようです。
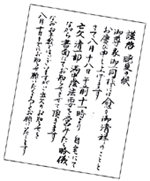
忌明け法要忌明け法要は、亡くなった日を入れて三十五日目、もしくは四十九日目に営む習わしですが、直前の休日に行う場合が多くなっています。
1.僧侶の予定を尋ね、日時、場所を決定します。
2.親戚関係、故人の友人関係など特にお世話になった方々を招きます。
3.日時が決定したら、なるべく早目に関係者に連絡します。
4.連絡は、電話またはハガキにておこないます。
1.忌明け法要までに、塗りや唐木の本位牌を用意しておきます。
2.掛軸・お花・線香・ローソク等の用意をしておきます。
3.忌明けを過ぎた白木の位牌は、菩提寺と相談して処置します。
1.会食には、引物をつけるのが一般的です。
2.お供え物を、皆さんに分け一緒にお持ち帰りいただく場合もあります。
3.手提げ袋や風呂敷を人数分用意し、持ち帰りに便利なようにしておきましょう。
1.忌明け法要までに、塗りや唐木の本位牌を用意しておきます。
2.掛軸・お花・線香・ローソク等の用意をしておきます。
3.忌明けを過ぎた白木の位牌は、菩提寺と相談して処置します。
喪主とその家族は、なるべく略礼服を着るようにします。
参列者は、略礼服か黒っぽい服装で出席するようにします。
法要の席位は、葬儀ほど神経質になる必要はありませんが、目上の方、遠方の方、故人と親しかった方は、なるべく上座にします。喪主は、法要の進行をつとめます。
法要の進め方は、宗旨・宗派や、会場が自宅、会館、寺院などにより異なりますが、自宅や会館にておこなう場合は、おおむね次のとおりです。
| 1 | 一同入場・着席 |
| 2 | 開式のあいさつ(省く場合もあります) |
| 3 | ろうそく、線香に点火 |
| 4 | 僧侶に合わせて、礼拝 |
| 5 | 読経 |
| 6 | 焼香(僧侶の指示により、参列者全員が順におこなう) |
| 7 | 法話 |
| 8 | 閉式のあいさつならびに会食の案内(喪主) |
| 9 | お斎(会食) |
| 10 | お開きのあいさつ(代表者) |
臨終から六日目の晩が逮夜で、宗派によっては逮夜法要を重くみます。故人の冥福を祈って一晩中語り明かす風習がありました。法要は期日を早めてもよいので、初七日は逮夜法要と合わせて一日前にいっしょにすませることが多くなりました。 初七日の法要は、実際には骨あげの二、三日あとにあたりますから、祭壇には遺骨、遺影などを飾ったままにしておきます。葬儀の続きのような雰囲気のなかで、近親者、親族、親しい友人、知人はもとより葬儀のときに世話になった人を招いて、僧侶にお経をあげてもらい、そのあと一同に茶菓や精進料理などを供します。地方によってはこの日を「精進おとし」として生臭物をつかった料理でもてなしたりします。また遠隔地から出向いた近親者がある場合などは、初七日の法要を繰りあげて、火葬場から帰ったあとの法要といっしょにすませることもあります。いずれにしても、初七日の法要で一区切をつけます。
二七日(14日目)・三七日(21日目)・四七日(28日目)は僧侶を呼んで読経してもらいますが、最近は僧侶の読経を略して家族だけで法要するところも多いようです。五七日(35日目)は、死者が冥土で五回目の審判を受けるたいせつな日として、親類、縁者、僧侶を招いて初七日と同じように手厚く法要を行います。宗派によっては五七日に忌明けする場合もあります。
七七日(49日目)は仏教では、この日の審判で死者の運命がきまるといわれ、忌日のなかでも重要な日とされています。さらに忌明けの日でもありますから、たいていの場合は、この日に近親者、友人、知人、僧侶を招いて埋骨式(納骨式)をし、そのあと精進料理を供し、大がかりな法要にします。葬儀のときは香典をいただいたところへは、忌明けのあいさつ状とともに、香典返しの品をおくります。仏壇のなかった家も四十九日の忌明けまでには、新しい仏壇を用意します。仏壇の扉は、忌明けまでは閉じておくのがしきたりですが、忌明け後は、朝、扉を開き、夕方閉めるのがふつうです。毎日、水とご飯と好物などを供えますが、朝夕、供え物をしたり、拝むときだけ扉を開いてもかまいません。また、葬儀のとき戒名を書いてもらった白木の位牌は、忌明けまでは遺影とともに祭壇に置きますが、忌明けとともに寺へ返し、代わりに塗りの位牌(仏具店で戒名を書いてもらう)を入魂供養して仏壇に納めます。

わが国では古くから忌服の制度があり、明治七年には武家の忌服制にもとづいて、太政官布告の“忌服令”が出されていますが、現在では形式的には厳しくいわれなくなりましたが、それでもやはり心構えとして必要でしょう。
一般には仏教の忌日の考え方に従って、死後四十九日までを忌服、死後1ヶ年を喪中としています。しかし、最近の考え方としては、官公庁の服務規定にある忌引き期間(表参照)を喪に服し、それ以後は社会的な仕事はとどこおりなく行うことが多くなっています。ただし、私的生活や心の問題としては、一般的な喪の考え方に従って身をつつしみ、故人の冥福を祈る心がけが大切でしょう。
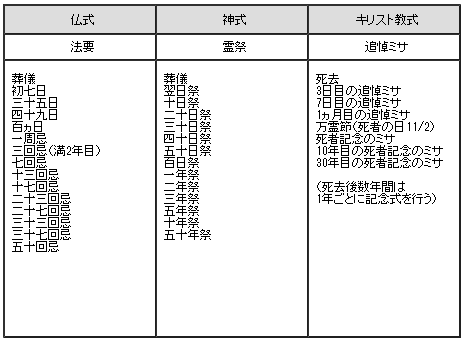
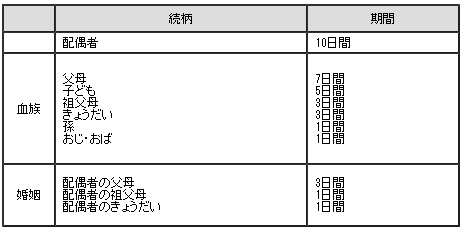
喪中に新年を迎えた場合は年賀状を出しませんから、例年賀状を出していた相手に対しては、十一月中旬頃までに年賀欠礼の知らせを出します。怠ると先方から年賀状が届いてしまい、新年早々にはさけたい喪の字のあるお詫び状を送ることになります。喪中欠礼のハガキは一種の通知ですから、死亡通知もかねて簡潔に書くべきです。ただし誰の喪に服しているかは必ず書き入れましょう。
核家族時代のこの頃は、大家族だった昔とは喪服の範囲もだいぶん変わりました。世帯が別ならば二親等(兄弟姉妹・祖父母・孫など)の間柄でも新年を祝う場合が多くなりました。

服喪中に新年を迎える場合、年賀のごあいさつは行いません。11月中旬頃までに、年賀欠礼のハガキを出すようにします。 年賀欠礼はがき
※喪中に年賀状をいただいたら、松の内を過ぎてから寒中見舞として返礼するとよいでしょう。
忌服中に近親者が亡くなり、忌服が重なることを“重忌喪”といい、たとえば、父をなくしてその忌期が終わらないうちに母が亡くなったという場合、母の死亡日からあらたに次の忌服を重ねます。
仏式では、四十九日(宗派によっては三十五日)をすぎると死者の霊がその家から離れるといい、この日を忌明けとします。神式でも五十日祭をこの日にあてていますが、キリスト教では、忌明けといったものはありません。そこで香典返しとともに忌明けの挨拶状を送ることが多いようです。また、忌明けの日には、寺や自宅(神式では墓前)に親類や友人を招いて手厚く故人の法要を営みます。なお、香典返しや形見分けもこの日に行い、葬儀のさいに神棚や額などに張った白紙も忌が明ければ取り外し、仏壇の扉もあけます。またそれまでの遺骨とともに安置していた白木の位牌は寺に納め、塗りの位牌を仏壇に納めます。ちかごろは四十九日を待たずに忌明けをする家も多くなりました。
1.忌明け(満中陰)七七忌に神棚封じを外します。
2.白紙で閉じてあった神棚は、忌明けに外します。
3.忌明け後は、普通にお参りをします。